 天気図
天気図
<最終更新日:
>
※今回修正/追記した箇所を、■にて色分けしております
天気図とは... | |
| 1 | 天気図は高気圧、低気圧、前線などの配置を表現するものです。その配置を気圧配置といい、冬にしばしば出現する「西高東低」の気圧配置はその典型例です。 |
特徴 | |
| 1 | 実況/24時間後/48時間後/72時間後の天気図を参照することが出来ます。 |
| 2 | 高気圧の中心付近は天気が良く、低気圧や前線付近は雨や曇りになることが一般的です。また、等圧線の間隔が密な地域で風が強くなります。 |
更新間隔 | |
| 1 | 3,6,9,12,15,18,21時の実況天気図があります。 |
| 2 | 「9時予想天気図」に関しては、(24h 後:速報12 時まで、確定16 時まで)(48h 後:速報12 時まで、確定17 時まで)(72h 後:確定12 時まで) |
| 2 | 「21時予想天気図」に関しては、(24h 後は06 時まで) |
着目点 | |
| 1 | 天気図は概ね10種類程度に分類できます。災害の起こりやすい天気図を予め知ることにより効果的な対策の策定が可能となります。例えば、大雪になりそうな天気図や霜害の心配される天気図など。 |
| 2 | 予想天気図のとおりに推移した場合は、各種予測情報の信頼性は高くなります。 |
注意点 | |
| 1 | 天気図のみから全て判断することは困難です。天気予報やアメダス画面など他の情報も活用することが大切です。 |
| 2 | 天気図から独自の判断をすることは危険です。天気図は地上の気圧分布によって描画されたものであり、気象現象は地上天気図のみでは説明できません。 |

|
天気図によく出てくる記号と用語
|

|
降雨予測や農作業計画、気象災害対策、出荷計画、販売促進等に利用できます。
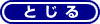
※情報提供元 : (財)日本気象協会